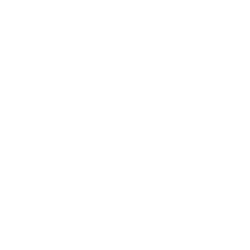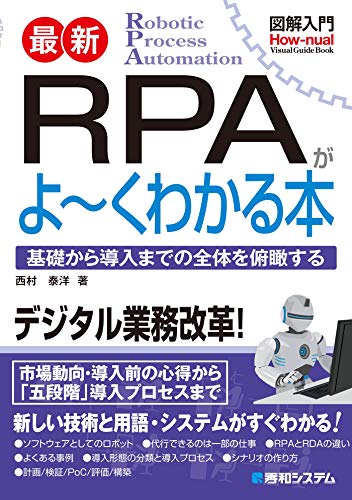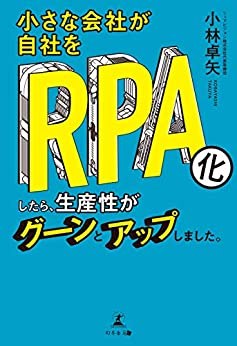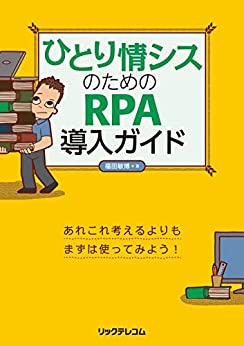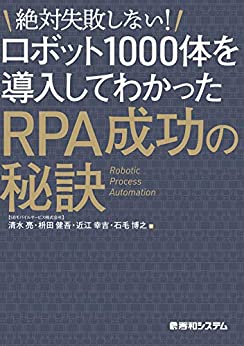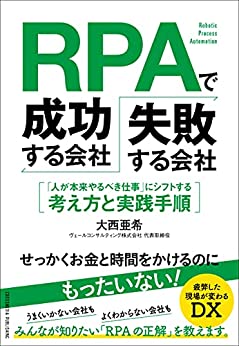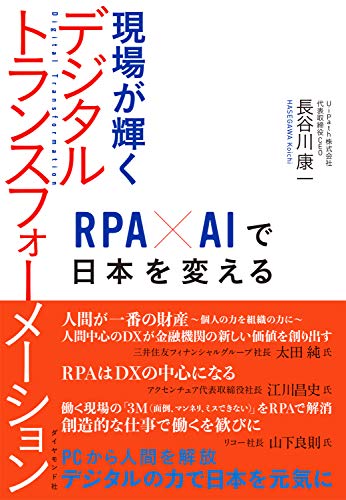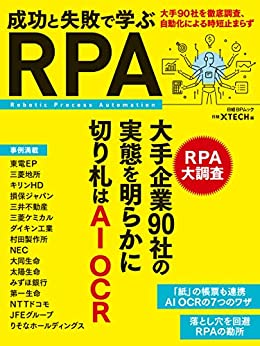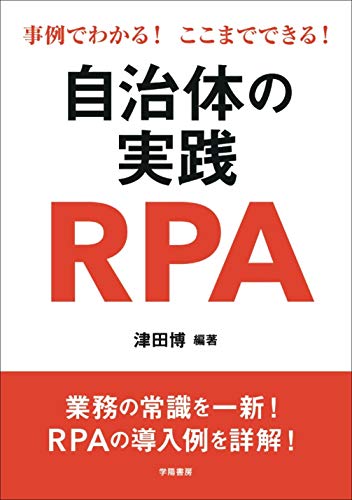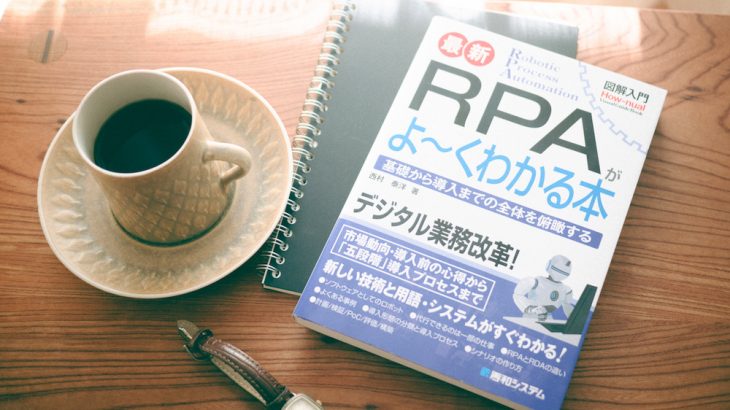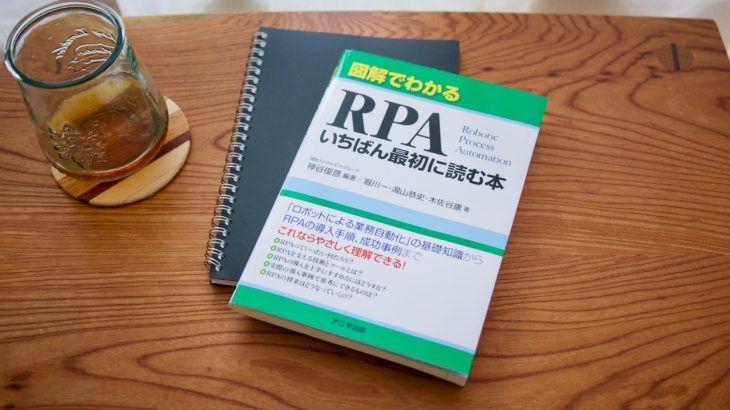この記事では「これからRPAについて学びたい」という入門者や初心者の方向けに、おすすめのRPA入門本をご紹介します。取り上げた本は初心者でも理解しやすい内容のものばかりですが、実務にもすぐに役立つよう、実例集や導入の体験談が書かれた本を多くピックアップしました。
RPAとは何か?
RPAとは「Robotic Process Automation」の略称であり、これまでPCを利用して人が行なってきた各種の業務をプログラム化・自動化することを言います。これまで人間が行なってきた事務的な作業をロボットが代行するため経費削減や生産性向上の効果が期待でき、業務改革の手法のひとつとしてとても注目されています。
RPA入門、おすすめの学習法
「RPAのことを知りたい、調べたい」と考える動機はさまざまですが、こんな状況の方が多いかもしれません。
- 業務改善をめざす経営者や責任者の方
- 会社にRPAが導入されたが、活用方法がわからない現場の方
- 話題のワードなので教養として知りたい方
上記のような事情により、これからRPAについて学びたいが「何から手をつけたら良いの?」という場合には、入門者・初心者向けの本を数冊読んでみることをおすすめします。
「本やウェブで勉強しても、あまり実務には役立たないよね」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに自分で実際にRPAに触れて動かしてみることは、どんな本を読むよりもリアルにRPAを体験する近道であることは間違いありません。現在は無料で始められるRPA製品やトライアル期間のあるRPA製品も多くリリースされているので、気軽に試してみることも可能です。
一方で、本には本の良いところがあります。多くのRPA初心者向けの本には「RPAのメリット・デメリット」や「導入の手順」「想定されるトラブルと対策」など、RPAに長く関わった人でないと経験できないことがわかりやすくまとめられています。これらは、RPA製品を短期間使ってみただけでは知り得ないことばかりです。
初心者向けに書かれた本で基本の知識を広く浅く頭に入れておくことや、多くの導入実例に触れておくことは、今後実務に取り組む上で視野を広げてくれますし、実際に導入を進める上で知る必要のある多くのこと(導入プロセスやトラブル対策など)を理解する助けになってくれるはずです。
入門者はまずこの一冊を読んでみよう
ここからは、「1からRPAについて学びたいが何から手をつけてよいかわからない」というRPA入門者や「これからRPAを業務に導入したいのでヒントを得たい」という初心者の方に特におすすめの本を、多くのRPA入門書の中から厳選してご紹介します。
RPA入門者・初心者におすすめの本9選
RPAの基礎知識を学べる本・2選
RPAについてまずは知っておきたい基礎知識や概要を掴むのに最適な超入門本です。どれも専門用語が少なく理解しやすいながらも、RPAの全体像を把握できるような内容です。
図解入門 最新 RPAがよ〜くわかる本|西村 泰洋 (著)
この本のおすすめポイント
今回ご紹介する本の中では最も基本的な内容の本です。著者は大手IT企業で20年近くIoT、モバイル、クラウド、ロボティクス、音楽配信などの様々な新技術を顧客企業に導入したり関連ビジネスに関わってきた方です。
RPAを売る側の立場の方が書かれた本なので、顧客に説明するようにわかりやすい言葉でRPAの目的やメリットが書かれています。
全体的に専門用語がとても少なく、全くの初心者でも難なく内容を理解できる本です。イメージしにくい概念も、わかりやすい例えを使うなど工夫されています。
この本の内容
本書は、RPAの市場動向および導入前の心得から「五段階」導入プロセス、用語までを図表をつかってわかりやすく解説した入門書です。RPAに興味のある方、導入を検討されている方などにおすすめします。
<目次>
第1章 RPAの基本
第2章 市場動向
第3章 ソフトウェアとしてのRPA
第4章 導入前の心得
第5章 導入プロセス
著者略歴
西村/泰洋
富士通株式会社フィールド・イノベーション本部シニアディレクター。顧客企業を全社的に可視化して経営施策の効果検証をするサービスの指揮を執っている。RPAの全社導入が経営施策の一つであることから経験を積む。二十年近くにわたり、IoT、モバイル、クラウド、ロボティクス、音楽配信などの、さまざまな新技術の企業への導入と関連ビジネスに携わる。
図解でわかるRPAいちばん最初に読む本| 神谷俊彦(編著) /深川一・湯山(著)
RPAの概要から導入の進め方まで、基本の内容をわかりやすく広く学べる本です。本書は全国の企業にコンサルタント活動や研修セミナーなどを行う経営コンサルタント4名によって書かれており、RPAの概念や歴史、現状の環境や課題などについても多角的な切り口でまとめられています。
研修セミナーの講師もつとめる著者のため、内容を理解しやすい工夫がされています。見開きの2ページに1つのトピックスがまとめられた構成は簡潔で読みやすく、多くの図やイラストが文字情報を補足してくれます。
この本の内容
RPAとは、これまで人間だけが対応可能と思われていた事務的な業務、もしくはもっと高度な事務作業を人間に代わって実施できる業務代行ツールです。ソフトウェア型のロボットが中心のシステムなので、「デジタルレイバー」(仮想知的労働者)とも呼ばれます。でも、それはいったい何者で、なぜそんなことができるのか、自分たちにも利用できるのか、などなどたくさんの素朴な疑問を抱くことでしょう。本書は、こんな素朴な疑問にズバリ答え、しくみや活用法が簡単に理解できるように図解入りでやさしく解説。インターネットや雑誌・新聞では入手できない情報も満載です!
<目次>
1章 RPAっていったい何だろう?(RPAの現状;RPAを取り巻く環境 ほか)
2章 RPAを支える技術とツール(RPAの構成と動かし方;RPAを支える技術 ほか)
3章 RPAを導入するときの上手なすすめ方(導入のための企画づくり;導入計画の作成 ほか)
4章 RPAの導入事例を見てみよう(事例の見方;業務・目的別の導入事例)
5章 RPAの将来はどうなっていくか(RPAとその周辺技術;RPAの海外事情 ほか)
著者略歴
神谷俊彦
大阪府出身。大阪大学基礎工学部卒業。中小企業診断士、ITコーディネータ、M&Aシニアエキスパート。富士フイルム(株)にて技術・マーケティング部門で35年勤務後、独立。現在、(一般社団法人)城西コンサルタントグループ(JCG)会長として、会員とともに中小企業支援を行なっている。得意分野は、ものづくり支援、海外展開支援、IT化支援。
RPAの導入の実際をイメージできる本・ 5選
実際にRPAを導入するにはどうすれば良いのか、導入するとどんなことが起きるのか?RPA導入による現実を初心者の方がイメージする助けになるよう、経験談や実務寄りの内容が書かれた本を選びました。
小さな会社が自社をRPA化したら、生産性がグーンとアップしました。| 小林 卓矢 (著)
自らが経営する会社にRPAを導入した経験談にもとづいて書かれた本です。著者が導入当事者という珍しい視点のRPA本で、他にはないリアリティあふれる体験談に触れることができます。RPAのメリットやデメリット、失敗や苦労などが正直に書いてあり、これからRPAの導入を検討する方の参考になる内容だと思います。短時間であっという間に読め、読み物としても楽しめます。
この本の内容
人口減少が進み人手不足が深刻になる日本では、生産性の向上が急務になっている。
その手段として注目されているのがRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)。
しかし、費用などの問題から導入できるのは大企業が中心で中小企業にはハードルが高い印象がある。
しかし、著者は自ら経営する会社にRPAを導入し、見事、大幅な生産性の向上に成功した。
情報集めから導入のドタバタまでコミカルに語る、実際に体験したからこその情報が満載の一冊。
<目次>
第1章 導入1年前/ネットで知ったRPA。注目されているけど、どんなもの?
第2章 導入半年前/まずは展示会で情報収集!小さな会社でも相手にしてくれる?
第3章 導入3カ月前/比較検討から導入決断へ。どんな業者が中小企業にピッタリか
第4章 いざ導入/事前研修からプログラミング。IT知識がなくても大丈夫?
第5章 導入1カ月/ここまでできた!ロボットを公開!
第6章 中小企業の導入支援へ/RPA化の効果と可能性。これほど生産性が上がるのか!
著者略歴
小林/卓矢
シェアビジョン株式会社代表取締役。2002年に明治学院大学卒業後、東証JASDAQ上場のコンサルティング会社へ入社。事業本部長として、中小企業向けに事業計画策定による金融支援から各種補助金申請のコンサルティングサービスの新規事業を立ち上げ、ものづくり補助金では2000社以上の企業を支援する。経済産業省主催の中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン策定検討会に検討委員として、ガイドライン策定にも関与。2017年5月にシェアビジョン株式会社を設立。設立2年で100社以上の企業支援を行うなかで、RPAの有望性に着眼。中小企業への普及を目指す。
ひとり情シスのためのRPA導入ガイド|福田 敏博 (著)
「システム担当者が1名しかいない会社」のシステム担当が、いかにRPAを自社に導入して業務改革をしていくか、一人しかいない弱みを強みに変えていくことができるか、という内容が書かれた本です。
3章では「まずは使ってみよう」として、RPAアプリケーションの選び方やダウンロードの仕方、EXCEL操作を自動化する方法などが紹介されており、初めてRPAを使う初心者の人の理解を助けてくれます。
一見「ひとり情シス」という狭いターゲットに向けた内容に見えますが、RPAの実践的な内容はもちろん、RPA導入の本当の目的や経営目線からシステム担当者が何をすべきかどう動くべきか、という内容が広い視点で書かれている良書です。
キャラクター2人の会話の掛け合いで話が進む構成も、楽しく読みやすく◎です。
この本の内容
本書は、RPAを基本からわかりやすく解説し、「ひとり情シス」が業務部門にRPAを導入して効果を発揮させるにはどうすればいいのかを平易に説明します。経営視点を持って取り組めば、きっと大きな成果を得られます。あれこれ考えるよりも、まずはRPAを使ってみましょう!
<目次>
Chapter1「ひとり情シス」とRPA
Chapter2 RPAを知ろう
Chapter3 RPAを使ってみよう
Chapter4「ひとり情シス」のRPA導入
Chapter5 RPAと「ひとり情シス」のこれから
著者略歴
福田 敏博
1965年 ⼭⼝県宇部市⽣まれ。
JT(⽇本たばこ産業(株))に⼊社し、たばこ⼯場における生産システムの設計・運⽤・保守等に携わる。その後、ジェイティエンジニアリング(株)へ出向。システムエンジニア、プロジェクトマネージャ、コンサルタントとして、産業分野での情報システムの構築を数多く⼿がける。
現在は、工場・プラントを対象とした産業サイバーセキュリティとRPA活用のコンサルティングに従事。技術⼠(経営⼯学部門)、中⼩企業診断⼠、ITコーディネータ、公認システム監査人(CSA)、公認内部監査人(CIA)、情報処理安全確保支援士、米国PMI認定 PMP、一級建設業経理士、宅地建物取引士、マンション管理士など計30種以上の資格を所有。
絶対失敗しない! ロボット1000体を導入してわかったRPA成功の秘訣|清水 亮 (著), 枡田 健吾 (著), 近江 幸吉 (著), 石毛 博之 (著)
ソフトバンクのコールセンター業務における巨大な業務効率化プロジェクトを実現したメンバーが、その経験をもとにRPAの基本事項から導入の課題、設計方法、成功の秘訣について書いた本です。入門者向けの内容としては難易度の高い箇所もありますが、RPAの基本から導入の方法まで包括的に書かれた本であること、実際の経験に基づいて書かれているため内容が具体的でイメージしやすいことから選びました。規模が大きめのRPA導入に携わる予定の方には特におすすめの本です。
この本の内容
7人で始めたプロジェクトはなぜ、日本有数の大企業で月間30000時間工数を削減できたのか?貴社にもできる「RPA自走集団」の作り方!巻末特別資料「お勧めRPAツール選定フローチャート」を収録!RPA導入プロジェクトを成功させる資料はダウンロードサービス!
<目次>
第1章 RPAの現状
第2章 RPA 導入時によくある悩み
第3章 RPA 導入判断
第4章 RPA 推進体制 「RPA自走集団」の作り方
第5章 BPRを考慮した本格導入のRPA設計
第6章 AIと連携する今後のRPA
第7章 まとめ RPA 導入成功の秘訣
巻末特別資料「お勧めRPAツール選定フローチャート」
著者略歴
清水 亮
大学卒業後、日本電信電話株式会社に入社。その後ソフトバンクコマース(当時)へ転職。ソフトバンクグループ会社統合を経て、ソフトバンク株式会社 カスタマーケアオペレーション本部 営業推進統括部 統括部長(現職)として全国約3,500店舗のソフトバンクおよびワイモバイルショップの店頭システムの企画・設計を行う。また、所属組織のコールセンターにおけるRPA導入/推進業務に従事。SBモバイルサービス事業開発本部長を兼務し、RPA推進および販売を行う。
RPAで成功する会社、失敗する会社 ――「人が本来やるべき仕事」にシフトする考え方と実践手順|大西 亜希 (著)
コンサルティングとしてこれまで100社以上のITや業務の改革に携わってきた著者が、その経験をもとにRPA導入の成功と失敗を分ける考え方や手順について解説した本です。
実際の経験にもとづいた生きた言葉で書かれていること、導入する企業の利益を親身に考えて書かれていることから、とてもわかりやすく納得しやすい内容になっています。
小さいことからまずRPA化することを勧めており、事例も具体的で「これなら自分の業務でもできそうだ」と思わせてくれるはずです。
この本の内容
「惜しいPRA」とは、「あと少しで成功するRPA」とも言えます。成功するか失敗するかは、実は導入前に決まっているのです。ぜひ、社員の生産性を高め、創造性を活かして楽しく仕事してもらえる環境をイメージしつつ、RPAの導入を考えてみましょう。
<目次>
序章 お金をドブに捨てる会社の「惜しいRPA」導入あるある9タイプ
第1章 RPAはどこに、どれだけ、どう使えばいいの?
第2章 「費用対効果」のウソ ――どこをどう考えて導入するのがいいか?
第3章 「人を削る」のではなく「人+ロボット」で2倍の仕事をこなす
第4章 で、導入の「仕切り」って誰がやるの?
第5章 【実践編】プロダクトはよくても、御社で使えなければお金のムダ
著者略歴
大西 亜希
ヴェールコンサルティング株式会社 代表取締役。
中小企業診断士、高度情報処理技術者。
みずほ情報総研株式会社、アビームコンサルティング株式会社を経て、現職。
これまでに大企業から中堅・中小企業まで、100社以上のITコンサルティング・業務改革コンサルティングに従事。デジタル庁 非常勤職員(ITストラテジスト)、一般社団法人 IT顧問化協会 副理事、学校法人 産業能率大学 総合研究所 兼任講師なども務める。
現場が輝くデジタルトランスフォーメーション RPA✕AIで日本を変える|長谷川 康一 (著)
タイトルのとおり、RPAとAIを活用することでいかに日本の企業の現場を「ふたたび輝かせる」ことができるか、というテーマで業務改革の手法について書かれた本です。
単純作業や煩雑な作業に疲弊している人であればうなづくような現場の課題があげられており、その課題をRPAやAIを使って解決することで真に人が活躍できる環境を作ろうという、「人」を中心にしたポジティブなデジタル革命についての考えが述べられています。
導入先進企業の経営者との対談が多く載っており、最新の導入例や経営者の考え方に触れることで多くの刺激があり、またRPA導入の前向きなモチベーションも得られるような内容だと思います。RPA初心者でも理解しやすい内容で短時間で読むことができます。
この本の内容
本書は、日本企業・社会が抱える課題に対して、RPAとAIがいかに効果的に活用できるかを、導入先進企業経営者等との対談も含めて、わかりやすく解説していく。キーとなるメッセージは、RPAは業務の自動化・効率化を大きく進めるだけでなく、人間の仕事を変えていく、つまり、人間がする必要のない仕事はRPAに任せ、人間は人間にしかできない仕事に専念できるようにし、日本の現場をふたたび「元気に」していくような力を持っているという点である。
<目次>
第1章 新型コロナウイルスが浮き彫りにした日本の課題
第2章 RPA×AIで日本を元気に
第3章 RPAで課題を突破する
第4章 現場が輝くデジタルトランスフォーメーション
第5章 RPA導入で人間は人間がするべき仕事を
対談 わずか3年で世界最高レベルのRPAとAI活用企業へ
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役 執行役社長 グループCEO 太田 純氏
対談 オフィスワークの“3M”撲滅で働きがい改革を
株式会社リコー 代表取締役 社長執行役員 CEO 山下良則氏
対談 テクノロジーを活用し、働く人をエンパワーする
パーソルホールディングス株式会社 代表取締役社長 CEO 水田正道氏
第6章 デジタルトランスフォーメーションを実現するRPA×AI
対談 RPAとAIが作り上げる新しい世界
AI inside株式会社 代表取締役社長CEO 渡久地 択氏
対談 RPAはデジタルの中心になる
アクセンチュア株式会社 代表取締役社長 江川昌史氏
第7章 デジタルの力で日本の未来を切り拓く
対談 茨城県の取り組みが世界のRPA活用モデルに
茨城県知事 大井川和彦氏
対談 夢を語り未来を構想する力を育む
筑波大学学長 永田恭介氏
著者略歴
長谷川/康一
広島県出身。慶應義塾大学法学部法律学科卒。30年近くのコンサルティング、金融業界での経験を持つ。アーサー・アンダーセン(現アクセンチュア株式会社)、ゴールドマン・サックス証券株式会社のほか、ドイツ銀行、バークレイズ銀行などでCIO(最高情報責任者)やCOO(最高執行責任者)を歴任し、ニューヨーク、ロンドン、シンガポールなど海外でのマネジメント経験を持つ。2017年2月に米UiPath日本法人であるUiPath株式会社の代表取締役CEOに就任。2020年4月より経済産業省「地域の持続可能な発展に向けた政策の在り方研究会」委員
RPA導入の実例に多く触れられる本・ 2選
企業や団体が業務にRPAを活用した実例が多く挙げられている本を選びました。初心者は「RPAでどんなことができるのか」を具体的にイメージすることができ、中級者以上は自社の業務に応用するヒントを得られるような内容です。
成功と失敗で学ぶRPA| 日経クロステック(著)
大手企業でのRPA導入の事例についてまとめられたムック本です。90社もの企業の導入結果の統計や16社の導入実例、6社の導入のワザなど、実際の企業の事例が書かれています。他社の事例からRPA活用のヒントをもらったり、また実際の成功例・失敗例から学びを得るのに最適の本です。比較的大きな規模のRPA導入に携わる方には特におすすめです。
この本の内容
本書では様々な企業における事例を中心に、RPAをどのように使い、どのようなメリットが出ているか、また社内の体制をどのように築いているかをつぶさに解説します。RPAとOCRを組み合わせて成功するための7つのワザも、紙の自動化に大いに役立つでしょう。
また、RPAを導入している企業の中には、思ったようにうまく行っていないところもあります。これらの失敗例を元にした「べからず集」も、これからRPAに取り組みたい人にとっては必須の情報となっています。本書によって、RPAがますます役に立つツールになること間違いありません。
<目次>
第1章 大手企業90社に見るRPAの実態
第2章 花開くRPA活用
第3章 16社・グループの事例で見るRPA
第4章 OCRとRPAを使いこなす7つのワザ
第5章 失敗に学ぶRPA導入の勘所
事例でわかる!ここまでできる!自治体の実践RPA|津田博 (著), 森正治 (著)
自治体のRPA導入に特化して書かれた数少ない本で、自治体の特殊な環境や業務内容における導入のポイントや実例がまとめられています。自治体の関係者の方に特におすすめの本です。RPA導入を先行して行っている自治体の導入の経緯や結果が詳しく書かれており、これからRPAを導入しようと考えている自治体においてとても参考になりそうな内容です。
この本の内容
国による自治体へのRPA(Robotic Process Automation)導入支援を背景に、全庁導入を前提とした実証実験を行う自治体が急増している。本書は自治体の担当者に向けて、RPAの導入によりどのような効果があるのか、そして実際に検討すべき点は何か、さらに導入の実際について先行自治体の最新事例をもとにまとめた!
巻末には、自治体のRPAの試行・運用・等に係る詳細なアンケートを収録。
<目次>
第1章「なぜ自治体にRPAが必要なのか
第2章 自治体RPA取組事例の紹介
第3章 RPA導入の課題
第4章 RPA導入手順
第5章 RPAツールの選定
第6章 自治体RPAの取組実態
〈付録〉RPAに関するアンケート集計結果〈抜粋〉
著者略歴
津田 博
香川県出身。近畿大学経営学部教授。住宅メーカー、滋賀県庁、福井県庁勤務を経て現職。その間、情報システムの企画・開発・運用及び調達を担当。現在、自治体情報化の研究に従事。博士(経営情報学)、技術士(情報工学部門)
おわりに
RPAの入門者・初心者の方におすすめの本9冊をご紹介しました。 「読んでみたい!」と思える本は見つかりましたでしょうか?
RPAについて初めて学ぶ方には、
- 専門用語が少なく理解しやすい本で「基本知識」「導入の手法」「導入の実例」を学ぶ
- 実際にRPAのアプリケーションを使って小さな作業を自動化してみる
ことをおすすめします。
現在は無料で気軽に始められるRPAアプリケーションもいくつかありますのでぜひ読書と並行して試してみてくださいね。今回の記事が皆さまの参考になれば幸いです。
無料で始められるクラウド型RPA「クラウドBOT」
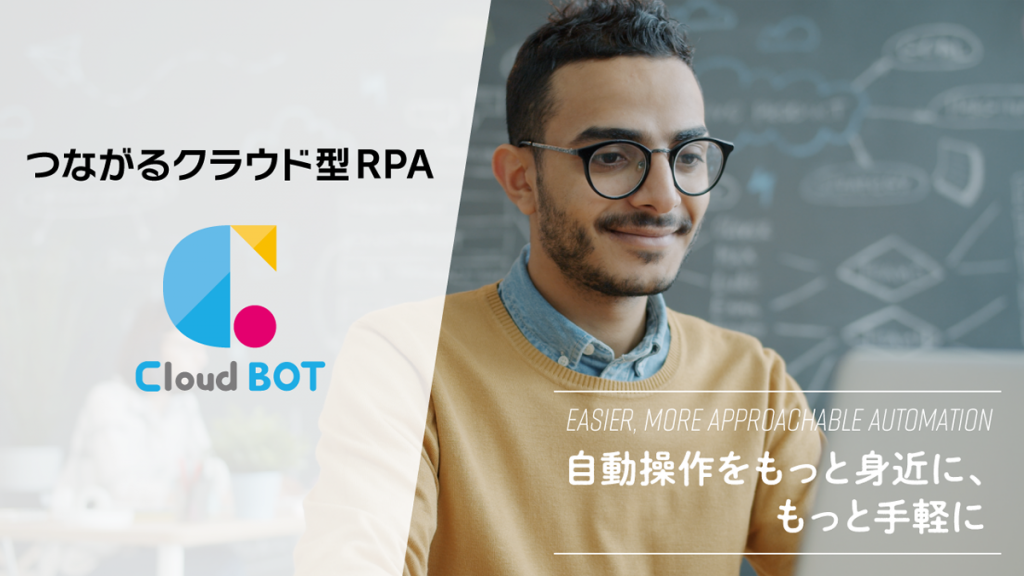
専門知識なしでWEBブラウザ操作の自動化ができる、クラウド型RPAの「クラウドBOT」です。無期限の無料プランがあり、これまでRPAを使ったことがない方でも気軽に試してみることができます。国産RPAのため操作が日本語で誰にでもわかりやすいこと、クラウド型のため普段使っているWEBブラウザ以外に特別なソフトを必要としない手軽さも魅力です。
クラウドBOT
https://www.c-bot.pro/ja